『円形建築』序
序
この度当研究所の所長坂本鹿名夫が独立してより、満五年半、研究所開設してより満四年を経て、ささやか乍ら、作品集を出版するを得た事を、当研究所の所員一同心より欣びに思う所であります。
実はこれは当研究所の記念出版として私蔵すべき物ではありますが、最近諸処方々より何か、当研究所の作品集のようなものが無いかと云うお問合せが参り、特に円形建築に就いて、参考書はないかという問合せが多いので、これを兼ねて、発表させて戴きたく思い、書律の好意もあり、出版させて戴く事になりました。
作者坂本鹿名夫の作品と云えば、円形ばかりであるように思われておられる方も多いようでありますが、前々からそうであり、特に最近では、円形に限らず、却て在来の角形のものが多い位にもなつて参り、又円形と角形とのcombinationの方も多く、どのように発展して行くか、我々所員間でも非常に興味を以て見守つている所であります。
作者の作品は謂はば、甚だ日本的とも謂うべきであつて、非常に経済という事を主目的としており、純粋機能派とでも称すべきか、芸術えの追求ということはむしろ二の次というような傾向もあるけれども、出来るだけ質素に、その建築の目的にかなえば宜敷しいと、即ち機能的な点だけを考慮に入れ、あたかも、船とか、飛行機とか、人工衛星とかに於ける近代工学の探求というものと同じ気持で、建築設計に当つている。勿論そこに美という事は恒に念頭に置いている事は、建築家として、勿論云う迄も無い事であるけれども、他の有名な方々のやり方の様に十分に経費を掛けた豪華な建築に較べて、甚だお粗末ではあるけれども寧ろ、精選された、一粍の無駄もない所が、まあ、世の中に受け入れられる所では無いかと我々は思う。
氏のその様な、極限迄、無駄を排除して、機能を追うと云うような性質は、氏の母方が山形県米沢の出であつて、上杉庸山公の遺訓を汲む旧家の厳格な教育の賜である事と、我々は考えている。氏の父君は元枢密顧問官故坂本釤之助氏であり、戦時中スイス公使で客死した前欧米局長故坂本瑞男氏は長兄に当る。また、文豪故永井荷風氏は従兄で、現日本ペン倶楽部の理事である作家の高見順氏は異母兄に当る。次兄坂本越郎氏はもと文部省官吏であり、詩人であり、現在は御茶水女子高校の校長である。又姉二人、妹一人はいづれも代議士又は銀行員に嫁し、その他、氏の親戚は凡て、文科系であつて、工科方面は氏唯一人である。
氏は東京生れ、府立一中、都立高校、東京工業大学を卒業後、大成建設に招かれ、設計主任として、十数年を過し、その間戦時中は海軍に引抜かれ、海軍技術将校として、やはり建築設計及び設営隊長として、国家に奉公した。現在は独立研究所を主宰し、秩父宮ラクビー場の傍に、自分の家の三階に事務所を載せた様な診らしい実験建物を建てて、専ら研究及び設計にいそしんでいる。坂本氏の前述の父君は福井、鹿児島両県知事、名古屋市長を歴任後、日本赤十字社副社長、貴族院議員等を経て、最後に枢密顧問官在職中に亡くなられた方であるが、現在は全然それらの縁故関係ではなく、全く氏の設計手腕を認めて依頼される人ばかりであるので、所謂親の七光りという事ばかりではないと思う。
現在、我々の研究所では、四十名以上になる若い学校出の技術者が皆揃いのビジネススーツで颯爽と働いており、夫々若いけれども、高度の技術を身につけて、氏の意を体して、次々と新しい研究及び設計に取り組んでいる。前述の通り、氏の作品は耽美派という意味での芸術作品は未だ無いけれども、機能的という意味での、楚々とした、はつたりの無い作風であつて、とにかく一点の無駄もない所から現在の戦後日本にマッチしているせいか、設計依頼者が門前市をなして、その応接に追われ、本業の研究の暇なき程の状態ではあるが、所員である我々としては、やり甲斐のある仕事だと思つている。
氏は今迄に無かつた、円形の合理的な面を率先して、研究し、取り入れた事に於ては、世界でも類が無く、1954年3月14日号のライフ誌(欧米版)に堂々4頁に渉つて、氏の作品が紹介され、同頁下段に紹介されたEero Saarinen(Eliel Saarinenの令息)の名が余りにも有名である為に、折柄Walter Gropiusに招かれ渡米中の清家清氏が逢う建築家毎に、「カナオ・サカモトを知つているか」と聞かれ、「もと私の学校の先輩で、極く懇意にしている」と鼻を高くしたと、記事切抜きと共に手紙を送つて下さつた程で、その後、円形校舎の記事は、欧米の雑誌にも転載され、英国雑誌には詳しい視察報告が載り、オランダの建築展にも写真が大きく展示され、米国、カナダ及びその他各国から問合せが沢山来たのも、非常に珍しいやり方であつた為と、又純粋に日本的な、質素に徹する設計のやり方が、欧米の建築家及び大衆にも何物かを与えたためと思われる。元々、氏の円形趣味と云うものは、非常に古く、昭和12年東京工業大学卒業の際の卒業計画も、円形の格納庫の上に、回転滑走路を設けた、高架飛行場であつて、この作品は、選ばれて、日本建築学会誌 昭和12年6月号に掲載されている。氏は学生時代よりアメリカのBuckminster Fuller氏の独創的な球形構造物の着想に、非常に興味を以て注目していたが、昨年Fuller氏が来日された折は、二回も先方より我々の研究所を訪問され、丹下健三氏、野生司義章氏や剣持勇氏、他多勢と共に夜半深更迄快談されたのは氏にとつて感慨無量な事であつたと思われる。
大体、作品集などと云うものは、作者及び関係者には興味のあるもの乍ら、余程の天才作家でもない限り、誠に無味乾燥、寧ろ滑稽なもので、良い恥さらしとさへ思われるのであるけれ共我々の研究所の設計方針と云うか、行き方は何か斯界の為に新しい道、方法を寄与したい、いわば開拓者の様な役割を務めさせて頂きたい、誰の真似でもない、神の命ずるままを具現して行く建築を造りたい、その結果、或は失敗し、人に嘲笑され、損をし、仲間割れをし、等々があつても致し方はない、我々はもつと高い大きな理想を抱いているので、結局は心の平静を取り戻し満足して死んで行けるのではないか、と云つた様な信念のもとに活きているので、恥も外聞もさらりと棄てて、兎に角、我々のやりとげた事を見て貰らおうではないか、その行き方は現代の流行となつた様式その他などからは遠いもので必ず多くの人は眼を背けるであろうけれ共、それでもそれらの人々でさえ一粍の信実には共感を呼び起してくれるのではないか、それで良いのではないかと考へた次第であります。余談乍ら現代の建築様式は余りにも一人の偉大なる天才――コルビジェ氏――の影響を受け過ぎ、無批判に、未消化のまま、自己作品の上に粉飾的に借色すると云つた傾向が多いのは誠に良くない事であり、もつと真隋を把え、精神をこそ汲み取るべきではないかと考えます。
今回このような拙ない作品をお目に掛けて、誠に汗顔の至りであるけれども、作者である所長坂本鹿名夫及び所員一同の意のある所を御汲み取り下され度く、又、これが些なりとも、建築界に寄与する所があれば我々の望外の喜びであります。(1959.6)
『円形建築』日本学術出版社(1959年)

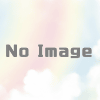

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません