法人立正交成会大聖堂
法人立正交成会大聖堂
東京都杉並区和田2-11-1
立正交成会大聖堂
東京都杉並区
設計 1956
施工 銭高組
面積 約23400㎡(7108坪)
工費 10億円(14万円/坪)
戦後、急速に信者の激増した立正交成会の本部と修養道場とを合併したもの。聖堂とは作者が建築法規その他より考えて提案し、そのまま名称となつた位で、初めは会長庭野日敬氏の着想以外詳細な要求は全然なく、故妙佼副会長が作者を非常に信頼し、一切を自由に設計させて下さつた。原案は右図模型の如くであつたが法規その他の要求で次第に変つた。中央は七階の内三階までは床があり、三階以上は吹抜でドーナッツ型、周辺の円筒状は廻り階段(昇りが楽)及び便所。
交成会にはこの他円形校舎2、前記体育館、円形青年会館、角形病院等を奉仕設計したが、実施予算は常に伏せてあるので、監理困難となり粗悪な作品許りとなり、遂には設計者の信用にまで影響した。
大聖堂の設計図は凡んど全部完成しており、躯体工事は完了したが、ここまで出来ると形体が判つてくるので諸説や妨害が出て、以後は施工業者下請の設計者により工事を進める事となつた。既に理解し難いパゴダ状の塔が載せられ始めている。一貫した指導精神なき設計では如何なるのか、会のためにも、建築界の威信のためにも惜しむ。
立正交成会は一時問題となつた霊友会より分れたもので戦前より独立したものであつたが、急速に信者の増加したのは戦後の事である。現在既に本部の他、修養道場と称する大講堂に類する建物が中央線中野駅より程遠からぬ地域全体に捗つて、宛然交成会町を具現するかの如き威観を呈している。建物の外観はすべてピンク色に色彩をほどこしてあるので一見してそれと分る。
作者が招かれたのは昭和29年の初夏であり、最初は男子高校、次に女子校体育館、病院、青年寄宿舎 次にこの大聖堂となつた。
当初は会の規模も現在の半分位であつたかと推察されるが、兎に角、要望事項としては何も呈示されず、唯々本部を造つて貰いたいとの事のみであり、一切を作者自身の空想より出発して今日の巨体を見る事となつた。
名称についても「本部」では建築物法に基いて、公会堂或はデパートの基準に律せられ、徒らに酷な制限を受けてはとの老婆心から、作者が会に薦めて「大聖堂」という名に改変して貰つたという一事もあつた位である。
会長、庭野日敬氏は我々にとつては不思議な位、建築に対しても、一種の透徹した信念を持ち、常に明確な判断を下した。又副会長、妙俊女史は作者を非常に信頼され、何でも作者の意の如く設計を進めさせて下さつた。然るに副会長は昭和32年に亡くなられ、会長一人となるや作者との間は急速に隔絶せる状態となり作者の設計理念など一貫すべきもなき有様となり6分通り完成した下図の如き状態のまま設計及び監理は作者の手を離れる事となつた。
総工費15億円にも達するのではないかと噂される大聖堂の工事も作者の綜合計画を離れて、後は徒らに中途より介入せる無知半解の手に汚されて、危怪な紛飾を施されつつある。作者として誠に愛児を手離すが如き愛着の念禁ずるを得ぬ有様であり、建築界の威信のためにも一大病根事に非ざるかの感が深い。
初期の構想は右図左側の如きものであり、この原案にて実施出来れば、世界にも珍らしい優美にして壮厳な建築となり得た事を信じて疑はない。惜しむべき法規に律せられ数多くの階段をデパート並に要求され、実施案に見る如く円筒状の外階段及び手洗棟を附加する事となつた。その折 心和む感慨は 都庁指導課の担当係官が、『徒らに作者の美建築を害するを恐る』との慰めの一語を与へられた事であつた。
本建築は三階迄は中央にも床があり、それ以上は中央に吹抜けとなつている。作者の国立国会図書館案と全じく整地に高低差のあるのが却て円形には有利に活用出来た。
大聖堂の目的は大祭典行事の他、日常支部毎に円坐を組み、修養に励むのに使用するため、劇場目的の他、平坦な座敷を広く必要とするので、かくの如き構想となつた。(巻末参照)
『それでも地球は廻る』の古言の如く最初の作者の設計は、たとえ中途から多くの人々によつて歪曲され、虚飾されようとも、交成会本来の精神と共に、建物は永遠にその任命を果すであろう事を信ずる。これが又あのように作者を信頼して下さつた故妙俊先生えの最大の贈物となる事を祈らずにはいられない。
『円形建築』日本学術出版社(1959年)


『円形建築』日本学術出版社(1959年)


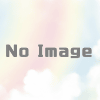


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません