『円形建築』私の提言
私の提言
坂本鹿名夫
幾ら民様からの御要望ありとは云え、かくも拙い私の作品を出版物にして戴く事は、実に耐え難いような、少なくとも時期尚早の感を深く致しますが、唯ここで躊躇し、恥じ入つて許りいてはいけない。寧ろ進んで世の批判を受け、特に誤解を招き易い殆んど建築界で始めての例であるらしい特許(私の場合は実用新案特許であるが)などについても、私の処信を申し上げて世に訴えたい事など、よい機会であると思い敢て書律の薦めに応ずる覚悟を決めました。
この書によつて私の独立満五周年の金字塔を築き、恐らく巻き起るであろう世の激しい批難により、次の五年間の私の方針のよき参考とも致し度く、又おこがましい乍ら一人でも賛同者を得、同志を結束する一助ともならば望外の喜びと思います。
★★★
私は「建築というものは、人の一生を容れる器(うつわ)である。」と思う。従つて、その器によつて、人の一生或は生命そのものが可成りの影響を受ける。勿論、器は人が造るものであり、好みの器を選ぶ能力のある人は良いが、何も知らずに あてがわれたものに 住む人は考えて見れば何と恐ろしいような又可愛想な事であろうか。
日本では昔から、清貧に甘んずるという良い習慣があつたが、これが又却て日本人の文化の進歩を妨げている場合が多いのでもあるが、しかし、私の建築に対する信念はまず、最も経済的に造る、と云う事である。建築はまず目的にかなつたものを、最少の経費即ち最少の空間、材料及び維持費等でまかなう事から出発する事。私は自らこのやり方を純粋機能主義と呼んでいる。
今の時代でも、例としては適切ではないかも知れぬが、二次大戦の影響を比較的受けなかつた諸国は、平和に馴れ、建築の世界でも、稍々耽美の傾向にあるが、新興の意気に燃えている国ではそのような傾向は少なく、生々とした美しさが自然とにじみ出ているように思われる。翻つて日本はどうであろうか。
戦争という、いまわしい病気によつて、脱皮したとは云え、まだ日本には色々な思想が雑然と入り乱れ、少しも統一がない。その事は建築界にもよく現われている。少し極端な云い方かも知れぬが、特に戦争中、国策に協力せず、独り勝手な行動をとり乍ら、敗戦後正しい理論家の如くもてはやされている連中の中に応々にして、そのような作品が見られる。
私は只々美を造る事をのみ目的としたような建築を嫌悪する。
私は美と云うものは自然に出て来るものであつて、創るものではないと信ずる。
少し余談で恐縮乍ら、例えば蒸気機関車が盛んに用いられた頃は、あの鉄馬の如き逞しさ、機械美といつたものを賛美する声が高かつた。しかし現代の流線型のガソリンカー、或は電気機関車の超モダーン型が出て来ると、はじめの内は馴染み薄いせいか、可笑しな感じがするが、段々見馴れて来ると、最早、古い機関車は単なる懐古趣味か、意地張り以外、美しいとは云い得なくなる。
重ねて云うが私は建築の美は、機能美に終始すべきもの、而も工費の最も経済なものであるべき事を条件とするものと信じている。
以下、五年間或はそれ以前より特に指名を受けて、設計したもの百数拾件の内より選んでと云うより、実の処を云うとたまたま写真の撮つてあつたものを集録し、私の処信を遂一御説明したいと思う。
私の作品と云えば、円形許りかと思われる方もあるようだが、それはシャボンの泡が、自然に最少表面積の球に落ちつくように、能率、経済を考えて、必然的に円形に落ちつく場合が多いのであつて、少しも作意や故意にやつているわけではなく、種々の制約のある場合は仕方なく、在来の角(矩)形にも、もつと自由な曲線にもなるのである事を記憶に止めて頂きたい。私は全体の形や特に細部の装飾(?)に捕われた現代日本の代表的建築を非常にあわれに思う。
私のこのような考えは、案外正しかつたのではないか。その証拠には、最近世界的な話題となつた、国際建築設計競技が二つ行われたが、その二つとも、一等当選は、今までの耽美主義者達を顔色なからしめた、極めて自由な魂を持つた逞しい設計意志に基く作品であつて、日本に於ても、急速に、逸早く転向、賛美者が続出する有様であり、余りにも節操の無さにあきれ憐れむ許りである。しかしこれを契機に、早く耽美派諸君の覚醒を望むや切なるものがある。
私としても、型式に流れ小娘のように作品を着飾つて見たい欲望に捕われる事はあるが、私の良心はそれを許さないし、又たとえ一人の設計依頼主が如何程裕福であり、虚飾を強いたとしても、社会全体が富み且つ潤ほはない限り、私は必要以上の贅沢をする気になれない。
建築は本来個人のものでなく、社会、人類、否、神に属するものであるからだ。
しかし、私の個々の作品を一見された方はよく、一つ一つが相当贅沢なもので、遊びがあるかの如く見られるが、それは丁度、ジェット機の流線型の機体からスマートな意匠を想起されるの類で、必要以上のものはなにもないのであり、試みに工費について調査されるならば、よくお判りになると思う。
本書の中に、その意味から或は多くの建築主の中には御迷惑になる場合もあるかと思うけれども、全体の利益のために、貴重な資料として、なるべく正直に工費を必ず公表させて頂いた。このような例は恐らく他書には絶対にない事だろうと思う。
一体に建物は不思議なもので、出来てしまうとなるべく高くかかつたように云いたいのが建築主の心理であるようで、この事が私の作品のような特殊な作風のものの発展をどの位阻害しているか計り知れない。円形校舎などというものは余程、金のかかつた、贅沢なもので、非常な利点はあるけれども、とても手が出せそうもないと云う人が多い。実際には正にその反対であるのに。可笑しな事ではある。
世の中が、公平に、すべての人が、不自由のない生活を営める世界になつたら、例えば、軽井沢人種のような間では、出来るだけ安く建てた事が自慢となつているが、早くそんな世の中になつて皆が正直に発表し合えたらよいと思う。
本書は対照を建築専門家ばかりでなく、建築に興味を持たれる方、――自分の一生を大切にしたいと思われる方、実際に計画なされる方にも役立つよう努めて平易に、写真や平面図により相当、具体的にも資料を提供したつもりである。写真と図と対照して見て頂きたい。
最後に、私の初期の作品である円形校舎を観て、討論会を開いて、意見をまとめて下さつた千葉大学工学部建築家の諸先生竝びに学生諸君の端的な批判を、私は、喜んで受け入れているので、再録させて戴く事にする。
★★★
(前略)――それは円形と謂う事で、何かDinamicなものを予想してきた我々には意外な位素直な白い建物であつた。建物は人間を暖かく包んでくれる母であろう。だから建築が人間を威圧するなど誠にナンセンスと云わねばならない。その威圧がこの建物には少しも見られない。それらをこの建物が比較的小規模であるからといい切ることはできないだろう。我々は小さい建物にも結構威圧的な仰々しいものを見て、反撥を感じることが多くあるのだ。経済的な理由もあつてそのエレヴェーションには洗練されたリズムが足りないとしても、この様な第一印象の素直さは単に円形という形の感じからくるのではなく、この建物の最大の魅力であり、最も成功した点でもある経済性と高度の敷地利用率とあくまで従来の学校の観念を破つて、学校を楽しいものに仕上げようとした設計者の意志が、その奥にある原因であるということを見逃してはならないであろう。
そして、この印象がこそ、この建築の本質的な課題が何であるかを物語つている。即ち現代建築ならばどれにも見られる機能と経済との対立、更に云えば、一人の建築家の中に宿つた“在来の物質的機能計画の世界を抜け出て一層高い意想の領域にまで、この建築を高めよう”とする建築家らしい魂と、この建築に要求され、且つ設計者自身も積極的にこれに協力した“建築を、従来のものより、より少い材料、工費で完成しよう”とする経済的な意図との対立が、又和解が、この建物の主題となつているのである。――(後略)(“近代建築”1955年3月号――建築情報社発行より抜萃)
『円形建築』日本学術出版社(1959年)
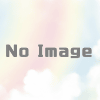
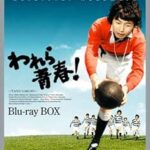
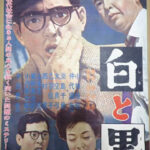


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません