『円形建築』§-2 円形建築の応用
§-2 円形建築の応用
円形建築は前記の如く有利な特長ありといえども、一般には使用者も設計者も不慣れな場合が多く、その特質、欠点等に習熟しない設計には屡々欠点のみ助長されて世の批判を浴びることが多い。(脚註――昭和32年11月18日朝日新聞大阪版の記事に大阪府八尾市に建つ三つの円形建物につき半頁に捗り批判あり、病院及び宿舎には適するが学校には不適であると論じている。この前二者は当研究所の作品であり、後者は遺憾乍ら似て非なる円形校舎であり勿論当所の作品ではなかつた。)
巷間屡々平面図ができれば建築の設計ができたように思う人があるが、採光、通風、音響、採暖等所謂建築衛生学及び構造学等専門的に精通し、風洞実験、照度測定、震動実験等々すべて研究し尽した上でなければその真価を発揮することはできない。
今の所、学校、病院、寄宿舎、ホテル、講堂、体育館、劇場、研究所、工場、社寺建築、庁舎、デパート等があるが、冷蔵庫、保温庫、X線室、原子炉、極地用建築、海底又は空中建築には次第に円より球形に発展して行くものと確信する。∫-1 円形校舎
(1) 発展の歴史
終戦後間もなく文部省管理局内に学校建物基準調査委員会が設置され、作者は当初は清水一氏(大成建設設計部長)の代理として出席を命ぜられていたが、後には臨時委員として管理局長より依頼を受け、民間では松田軍平氏の他は作者一人で、他は大学、建設省、文部省の専門家許りの席上、木造校舎の規準、補強、老朽対策より、次は鉄筋コンクリート校舎の規準に及んだ。当時文部省編纂、建築学会より出版せる規準、A.B.C三種類の校舎一般図、矩形詳細及び構造計算規準の内、構造以外は作者の担当せるもので、戦後の人も物も少ない時とはいえ実にひどい図面でミスも多く汗顔の至りであつた。唯図面を作るについては会議の結果の大項のみ守れば、細かい工夫等は比較的自由にまかせてもよいという事であつたので光線対策その他作者の着想を折込む事ができ、今でも遠隔の地で作者の光線反射板やルーバーや、屋上排水溝の採り方等々、会議の席上で出なかつた作者の考案が実施されているのを見ると、誠に嬉しいような又責任の重大さに身の引きしまる思いがする。
しかし今でもそれらの解決方法は決して悪いものではないと信じているが、更にもつと良い方法を考案したので、本書に於て見て頂ければ幸甚である。
その会議の席上、占領政策である自主的学究法即ち在来の教室内にもっと掲示板やホームライブラリー(派出図書館)をとり、学生の意志発表や自ら進んで学び取る学習法等を奨励することとなつたため、在来校舎では教室の廊下側の窓を全部閉鎖し、ここに掲示板をとる事としたところ、一夏過して見て、日本の気候には全然不適当であることが判り、根本的に対策を要求された。
その結果、作者の考案したものが扇形教室であり、左右の壁面は余す所なく掲示板、学生用黒板、書棚等になつていてしかも通風は完全であり、採光、音響的にも理想的なものを工夫した次第であつた。
作者が幼少より円形建築に興味を持つた事は既に序文に記してあるが、実際に設計図を世に問う機会に恵まれたのは昭和23年東京都が西戸山アパート団地にモデルスクール建設を計画した時に始まる。当時、都建築局学校施設課(現在営繕第二課)の依頼により文部省、建築学会の三者一体の委員会ができ、官民より選ばれた各委員が各自私案を持ち寄つて検討会が開かれた。敷地は西高東低で整地にかなりの費用を要することと、建設資金が一度に出ない事から、作者(当時、文部省管理局学校施設規準調査委員会臨時委員)の案はまとまりのよい円形校舎を二棟任意の位置に建設し、後から共通部門で連絡するというものであつた。更にもう一案馬蹄型の校舎を提出したがこの案に類似したものは後に文部省の指導により北海道に実施されたと聞く。しかし扇形教室は当時世界に類なく、特に背面採光の着想は絶無といつてよく、グロピウス、ライト、ノイトラ等による馬蹄形校舎に於ても側面黒板を使用し、採光は側光或は天窓等によるものであつた。当時同席した委員の中には文部省田中施設部長をはじめ、中尾(当時指導室長)、栗山、池田及び都建築局の久保、池田の諸技師をはじめ、故遠藤新、松田軍平、池田陽、内田詳哉等の諸兄約二十名がおられたが、面白いが奇抜すぎるとのことで採用にならなかつた。一人故遠藤新氏は後日真赤に加筆された青写真を渡され、大いに作者を鼓舞激励された。
昭和25年頃丹下健三氏の広島児童図書館に扇形のレクチュアルームが出現した。(国際建築1950-10)昭和27年早々、石川県金沢市の私立金城高等女学校に円形校舎第一号を実施するの機会を得た。これは作者に個人的に相談を受けたものであるためこのように思い切つた事ができたが、実施設計に当つては当時の勤務先である大成建設設計部に持ち帰つたため先輩達からは随分と批判を浴びたようであるが、今は昔の感が深い。構造は外註という事になり、故小野薫先生にお願した。なお第一回作は種々の制約から甚だ不本意な作品となつてしまつた。
昭和29年独立。当研究所の自由な立場から第2号円形校舎を東京練馬の山崎学園富士見高校に実施した。1号は思い通りの設計にならなかつたのでこの2号が作者の自由第1号ということができる。しかし、これとても現在はスーパーデラックス型にその席を譲り、既に過去の型式となつたが、その歴史的意義は深い。(2) 円形校舎の説明――附・円形校舎の特許(新案)について
円形建物としての利点については前記参照され度、特に校舎について述べると
(イ)管理のし易い事――工事中にもあてはまる。
(ロ)歩行距離が短い事。
(ハ)敷地面積に比し収容力の大きい事。
(ニ)教室が扇形である事の利点は次の通り。
教育上の効果――扇形であることは教師、学生両方から理想的である。教師と学生の距離が短かく、集中的であり、親密感を増し、教師は掌握が容易であり、視野が広く、黒板が光らず、両壁面はそのまま掲示板となりホームライブラリーなどがとり易く、戦後要求された自主的学究法に適する等である。
その実施に当つては、関係各官庁の種々の制肘に会い、且つ現在法規が、主として角形建築を対照とするために、甚だ法規の解釈に困難を来し、『作者の如き良心的な設計であればよいが、もしも心なき設計者の手に委ねたならば一見似て非なる円形校舎が罷り通る事になつて、取締りにも困難を来すという理由から、出来得れば、これを特許にでもして、危険な作品には改良を加えてもらうようにしては如何か』というような事を示唆されて、心ならずも特許を申請した所、意外に早く許可が下りた。
このように作者としては、苦労した作品であるから大事に育てて貰いたい。円形校舎というのは斯ういう風に作ればいいのだという事が、丁度角形の校舎がどんな素人が作つても大過なく出来ると同じように、これだけの理屈を心得れば大過のないものが出来るということが判るまで、作者がそれを烏滸がましいようだが指導してゆく。それには作者が独占的であつてはいけないという心構えから、絶対に特許料というものは取つていない。而かも今までは設計したいという人があれば、青写真を数校分を無料で差上げたり指導してきた。然るにその結果はどうであつたか、今まで相当有名な設計家でも、円形校舎に関しては、まだまだ研究不充分であり、只、徒らに金額が嵩むばかりであつて、一向に大事な急所を押えてはもらえないために非常に世の批判を招いたり、使用者側に迷惑をかけたり、誠に遺憾に耐えない次第であつた。このような例は枚挙に遑がない程であつた。これでは折角出来た円形校舎までが、世の中から冷い眼で見られたりする現状である。
既に当方では、円形校舎の実施例も100以上となり、最近では相当自信のある作品も出来るようになつた。
現在まで、日本中に建つた円形校舎は殆んどといつて良い位、当所の作品の影響で建てられたものが多いようであり、或は幾分なりとも参考にされた事と思うけれども、新聞、雑誌等で批難を受けるのは主として採光、騒音、通風等の問題で僅かな注意が足りないものが多く原理がよく判つていないものが多いようである。当方が全然知らぬ間に建ち、見たこともないものは、山口県荻、沖縄那覇(これは半円形で昭和29年頃、鹿屋市役所建築課のために作者が設計したもので、鹿屋市立小学校に二棟建つた。その設計図が流れて行つたものと思う。)、北海道石狩及び北上、他一校、愛知県有松町立小学校及び大阪府八尾市南山本小学校以上の七校で、荻のものはカソリック系の学校であると聞くが、その後キリスト系の学校より円形校舎の建立の話が出ると必ずといってよい程、荻市の欠点が持ち出されて中止となるのが例である。那覇市のは評判悪しく、南九州地方で当分防害となつた。鹿屋市のも作者の名は一切出さぬよう要求され、監督もせず、外観は設計図通りに出来ているらしく、写真は新聞で見たが、内部は色などどうなつているか、評判も余り聞かない。
愛知県に至つては案じていた通り、有松町の結果を見て県教育委員会の激怒するところとなり、今後当分県下では円形校舎は建てさせぬとの事で、その後、尾西市の高等学校などは二棟円形許りで建てたいという校長及び教頭の非常な熱意があつたにも拘らず、制止させられたと聞く。有松町は当時の町教育委員長の特命で某一流工務店の設計施工下に建てられたものであり、間取りは作者創案のものと全然同様であるが、詳細は見せてもらえなかつたし、当方で注意した事も施工してないのではないかと思う。これこそ、特許侵害が立派に成立するものであろうが、名古屋は作者の亡父や作者の故郷ではあり、いつかは真実を知られる時もあろうかと時期を待つことにしている。その工務店はその後、トヨペットの事務所やナショナルの工場に作者の円形校舎とそつくりの建物を設計施工しているのは円形建物の利点を感知しての事と思い、作者は寧ろ喜んでいる。
北海道のは遠く金沢市及び長野県飯田市等にある作者の作品を見学した後に設計したとの由であるが、最悪の円形校舎といつてもよく、害毒を流すものであり、この中で教育させられる児童のことを考えると暗澹とせざるを得ない。その後、余りよい出来ではないが当研究所の作品が道内だけで七棟、目下設計中二棟、病院完成のもの三棟出来たので、真実を見てもらえると思う。
大阪府八尾市のものは十六角形校舎と称しているが、某一流新聞では円形校舎評判記と称して、批難を遂一列挙し、関西一帯の円形校舎に一大衝撃を与え、父兄を混乱させ、新入生を減少せしめる程の大事件となつたが、当研究所の作品でない事が判明して漸く治まるという一コマもあつた。しかし今でもその後の発展は急激に止り、却て東京近辺特に横浜市に発展するようになつてしまつた。この八尾市のものこそ、完全に侵害の対称となり得る間取り及び構成である。この場合市長がわざわざ詫びに来られているが、建築主及び使用者には何等責任はない。又法律上は施工者にありというが、作者は寧ろ設計者にありと考えている。
以上のような事実を以つてしても大衆の利益になる建築上の考案が正しく普及することを防害する、悪質且粗悪な模做作を取締る法律はないものか、目下の処、特許或は新案又は意匠登録位しかないとは如何なものであろうか。
以上の場合、或円形校舎の有る学校では、その新聞社に抗議した処、作者より概設計者乃至施工者に対し特許(新案)侵害の訴訟を起した方がよい。そうすれば大きく訂正記事を書くとの事であつた。
その後円形校舎の正しいあり方について大きな訂正記事が出たが、最早汚点は拭ううべくもないらしい。
その他、作者の作品でなく他の設計者又は建築主より直接又は間接に模做する事を申入れて建築されたものは次の五校である。即ち東京新宿文化服装学院(三菱地所部)、滋賀県安土町立中学校(田中、小西設計事務所)、大阪府松陰女子学園(大阪建築事務所)、仙台常盤木学園(山下寿郎事務所)及び兵庫県波賀町立引原小学校(高橋事務所)、千葉県習志野市立高校他一校(東京設計事務所)。
これらのうち、あるものは仕上や設備は申分なく又豪華なので工費も莫大であり、安いものでも当所作品の同様のものに比し、五割以上高いのであり、それだけの良さは必ずあると思うけれども、例えば音、光、通風及び危険対策等に対し大いに疑義のあるものがある。
又建築というよりも寧ろ広告塔のようなものもあり円形校舎とはかかる軽兆なものであるかの如き印象を与え、心ある教育関係者が円形校舎を正しく認識するのを防害するかの感があるものも出来た。(3) 採光
背面採光によるも、二次(反射)光線による天然の間接照明により陰影を作らぬため、学生の机上は手暗がりにならず、教師の机上も非常に明るいため、教師の瞳孔は窓を見た時も左程開いていないため想像よりは眩輝を感じない。参考:昭30.3.13 東京大学平山教授研究室調査建築学会建築設計々画規準委員会提出資料(抜萃)――照度測定山崎学園 昭30.3.13(日)晴
1) 教室に必要とされる照度は100ルックスである。太陽の反対側の教室で人の影で測つた机上の照度でも100ルックス以上はある。人のいない机上は最低でも600であるに反し、角形校舎では太陽直射面の教室でも最低は120でしかなかつた。
2) 黒板の照度は太陽直射の角形校舎と太陽の反対側の円形校舎と大略同じ値である。円形校舎の正面黒板は太陽が横より斜めにあたる場合でも大体平均されている。角形教室は横斜め後より光線が当つていたがそれでも両端で相当に変化がある。(一例1040ルックスより600ルックスえと低下する)。
3) 人、側壁及び柱等の反射光によつて測定値が大きく影響を受ける。(作者註――これは反射光が照度分布に大きな役割を果す事を実証し、空室或は小人数着席でなく多数着席の場合意外に明るくなることを裏書きする。
東京大学平山教授研究室測定結果説明(作者)図及び写真で見る如く円形及び在来の木造二階建校舎(矩形)を対照として測定をされた。ちなみにこれは学生の卒業論文の参考にされたものであつて。当方よりお願いしたものではないが、ここに転用させて頂き感謝の意を表する次第である。
当日は休日で全館人はおらず、窓は全部閉められたままであり、三月とはいえ夜来の雨が上り急激に暖風が吹き、よく春先にある気温急昇し、石及びコンクリート等はすべて俗にいう汗をかくと云う特種の状態で室内の方が外部より余程冷い位であつた。従つて照度測定後、同日に湿温度をも測定され、西日の影響について云々されているが、作者をして云わしむれば、これは些か酷であり、欄間(流風を考慮して教室側に下方突出し、上釣り元のもの)及び出入口扉の腰は開閉自由のガラリになつており、空気の流通をはかれば、相当快適な気候状態になる事は、その後の使用状況からも満足な結果を得ている。特に夏期は外窓をも全開するので室温及び通風は測定時とは大部異なる。
しかし、照度測定については何等不公平なき平常の状態であつたと考えられる。
測定対照は山崎学園の円形校舎と在来の木造(矩形)校舎とでは不充分であり(写真参照)、最新型円形校舎と三次計画にて新築した鉄筋コンクリート造矩形校舎とを近く測定するので比較して頂きたい。
測定は朝9時30分より行われ、図中10.9.8.7.6教室(すべて二階)の順に行われ、10時45分に終つた。矩形教室は更に太陽光線の強くなつた11時30分より11時45分までに測定した。
円形教室はNo.8教室が正南中し、木造矩形校舎はすべて正南中している。それにも拘らず、円形校舎の太陽に反対側の教室の最悪の場所ですら、在来矩形校舎の倍以上はあつた事になる。
図(A)は円形校舎二階平面図 (B)は矩形木造校舎の二階一教室のみ その他6教室のみを取出し、背面光線の場合の机上の明るさを、つまり手暗がりにして測つたもの、但し単独(一人)着席して測つたものもあるが省略する。多数同時に着席している場合は反射光により更に明るくなる事は報告書の中にもあり、実際に使用しても判つた。
本測定は作者の初期の円形校舎であり、これは窓の外にベランダ巾1米のものがついているがその後窓上の梁が天井従つて室内をも暗くするのでこれを室内え移したり(帝塚山第二期その他)、あるいは無くしたり(鳥羽中学)、更に窓の外側に手摺補助として廂ようの光線反射板を付けたりして、光線の導入を計つた。これらは更に良いものとなつている事は確信をもてる。但し両側壁の反射と色工合の問題、又唯いくら明るくても、光の対比の関係で教師が眩輝を感じる問題も注意を要する処である。しかし対策はいくらでもあり、解決は済んでいる。設計上注意すべき点である。(4) 通風
通風は各階毎に行われ、中央廻階段より屋上え抜ける事は少ない。中央換気孔は寧ろ冬季熱気の自然上昇を誘い損失であつた。最近のものは各階をワンルームとし、取扱えるよう工夫し南北一様の温度になるよう成功している。夏季涼風は風上に適当な導入孔があれば風下の各室も可成りな涼風を得られる。これは中廊下式の校舎に比し非常な利点である。
参照:昭31.9日本建築学会研究報告第54号 佐藤鑑――円形校舎の通風に関する研究 日本建築学会設計々画パンフレット3-2.1 円形建物は通風上有利か。(附)――爆風と円形校舎
円形断面の煙突が風圧に対して直角方向に揺れるという珍らしい事実はその道の専門家なら誰知らぬ人もない事ではあるが、円形建築に対する風圧の実験は未だ完全なものはない。今回、長野県飯田市附近に発生した爆発事件によつて現場から146mの地点にあつた円形校舎――市立浜井場小学校――は非常に珍らしい現象を示した。
(1) 円形校舎の規模――鉄筋コンクリート造三階建一部四階(音楽室)直径29米、各階を八等分し南方に普通教室各4、北側に特別教室(普通教室の1.5倍)各2、各便所及び階段を有するもの。建具は木製、引違戸である。竣工は昭和30年5月。
(2) 爆風の強さ――昭和34年5月29日午後2時30分花火工場が一大音響と共に爆発し飯田市の全壊家屋24戸、半壊74戸その他2000戸以上に被害を及ぼした。爆心地から約600米の飯田測候所の地震計では震幅0.2㎜でこれは有域地震2で戸がバタバタする程度の弱震に過ぎなかつた。従つてこれは爆風及び爆音による空気の振動による被害と推定される。家屋の被害は爆心地を中心として半径1KM内外の家屋はガラス、障子等の若干の被害、半径500m内外ではガラス、障子等の他、壁の脱落を認め、200~300mではガラス、障子は100%の被害の他屋根瓦、壁、天井等が破壊され、木造校舎の南面下見壁は内部漆喰壁共押し出されている箇所も見られた。
(3) 円形校舎の被害――今回の事件によつて得た貴重な事実は、円形校舎にこの様な風圧の作用した場合、建物の受ける正圧は風上の二教室(円の1/4)位のもので両側面及び稍々風下に位する教室では完全な負圧即ち吸引力を受け、建具及びガラスはすべて外部へ吸出されている。完全な風下では一、二階は全然被害を蒙らない処を見ると圧力零であるが僅かな真空状態を呈した程度で、三階は稍々吸引力を受けた箇所も見られる程度である。
この事実は既に大体想像され又飛行機等の超スピード流体力学では既に実験済みの事と思われるが、円形建物にこの様に判然と記録されたのはこれが始めてではあるまいか。即ち風上の二教室では建具及びガラスの一部は室外へ破壊しているが、僅かでも側面になつた部分では外方に倒れていて、それもホンの一部分にしか過ぎず、少しでも風向と直角に近づけば、凡ど被害は零に近づく。
(4) 児童の傷害
爆発時運動場にいた者は爆風の衝撃で転倒し、その為に怪我をした者が多く、多くは打撲であるが、不発弾に頭を打たれて即死一名又花火がグランド内で爆発し火傷二名を出している。校舎内では恐れていた爆風によるガラス破片の飛散による裂傷というものは凡どなく、多くは足又は脚部の傷者が多い。それも一階に少なく三階に多い。特に四階は風上の扇形の側壁が全部ガラスであるため、足に火傷を蒙つたもの、頭にもガラス傷を受けたもの等が出た。繰り返して云うがこれらはいずれも風上の円の1/4の部分のみに限られ他の3/4は無傷であつた。これに反し在来型の四角校舎では風下に偏したガラス迄飛散している。
(5) 説明――以上は前記、亀井勇博士を通じ氏の高弟で現在長野県長姫高校 建築科教諭である桑島博氏に調査して頂いた報告書に基くものである。この円形校舎の建具枠は断面が楔状をしているので内方えの正圧には強いが、負圧即ち外部えの吸引には極めて弱い構造であつたため、その部分の被害が非常に非道く現れている。しかしそれは前述の通り内部の児童には何等影響のない事であつたのは幸であつた。当時の新聞紙上に円形校舎の被害が誇張されていたのはその箇所を示すものであり、附近の木造家屋が凡ど原型を止めないのに比すれば、如何に安全なものであるか、寧ろ余りにも毅然として聳立していた事が報道陣の注目の的となつたものと解しても良いと思う。建築学会設計々画パンフレット
円形建物は通風上有利か
設計上必要な解答
扇形の一面のみが外気に開放される場合で考えると、矩形室で一面のみが外気に開放されるものより有利である。これは曲面の風力係数の分布が、矩形の一辺における分布より、その変化がいちじるしいからである。しかし、円形建物の半径が大きくなり、扇形室の曲率がゆるやかになると、その特色が失われる。また、風背側120度の範囲では風力係数の変化が少ないので有利とはいえない。中央ホールを通しての通風で考えると、矩形の片廊下式で廊下を通じての通風に比較すれば決定的に不利であり、中廊下式で廊下を通じての通風に比較するときはあまり差異が認められない。ただし、中央ホールの室内風力係数を高めるように、風向側から風の導入をはかると、風背側の通風を高めうる。
また、中廊中式では、廊下に平行な風向となると通風上非常に不利となるが、円形では如何なる方向の風をうけても通風上は等しい性格を示す。
横浜国立大学 佐藤鑑教授研究室測定
通風及び音響に関する研究
説明(作者)――写真の如き縮尺四十分の一大、セルロイド製模型により、窓は引違に合せて開放型式をとる。これと片廊下式及び中廊下式の校舎と比較した場合、円形校舎では如何なる方向の風を受けても、風上側より風を導入するよう開孔があれば、即ち窓を開ければ、風下側でも充分通風がある。
この他、扇形及び曲面硝子窓の原理より、単独教室のみ内でも循環通風がある。
建築学会設計々画パンフレット中、誤解を招き易いのは、上記、循環通風測定の場合はそれのみの測定を云々するので、風下側は不利であると記してあるが、実際には上記でも判るように、風上より同時に導入風もあるので風下側は循環通風はたとえ不利であつても充分、更に潤沢なる貫通々風がある訳で、全体としては少くも不利ではないわけである。(5) 音響
教室内の音響は扇形であるため、理想的であり、音楽教室にはわざわざこのような形をしたものがある位である。教室と中央ホールの境の扉を開放していても教室内の音は外片へ逃げてホール内えは大して入つて来ない。又隣室の音及び向い側の教室の音も在来校舎に較べて有利であり、ホールに吸音材を使用すればこの効果は完璧に近くなる。
参考:前記佐藤博士の同論文、山崎学園の場合はホールの吸音は天井繊維壁にのみ頼り、周壁はブロック化粧績のままであり、その後天井は木毛板あるいはニッポールの類、壁は吸音コペンハーゲンリブ等の併用によりこの面の批判は全然解消した。――例帝塚山学園第一期円形校舎、関東商工、目白学園、梅花学園等、(6) 日照
作者の円形校舎は極めて日本的条件即ち採暖、涼風共すべて自然を利用し費用の嵩む人工換気設備はなるべく用いない方針であるため、以上の如き工夫を要するが日照の問題は採暖の他衛生及び気分的問題もあるので最も重要視すべき項である。
即ち南側の3乃至 教室は寧ろ良好過ぎ、冬季の射入に対しカーテン(窓上、中、下三段の内、中段のみでよい)を要するが、北側に偏する教室は半日しか日照がない。又夏季暑い東西の射入光がある。これらに対しては充分考慮して対策を講ずる必要があり、現在のところ、余り苦情は聞かない。
昔から精密な仕事は北側で行えという位であるから要するに冬季採暖さえ考慮してあれば寧ろ教室としては北側が推奨できる位である。まして半日は日照があるのであるから、角形教室の北側教室の比ではない。自然採暖方法としては前述の如く南北同温度になる工夫がしてある。∫-2 体育館
円形ドームが体育館に適している事は、目ざる、籠等の構造より何人にも容易に想像のつくところで、最近の円形校舎の屋上には必ずといつてよい程、体育館兼講堂を設ける事になつた。これを地上え別個に建てれば坪当り4万円以上するものが、僅か2万~3万円で出来る利点がある。又屋上の場合は梁なしでも2m位は廂をはね出させて、下階より広く大きくとることができる。(実例)
高崎市立女子高校は地上に造つたが中二階を持ち直径36m(20間)でバスケットコートを二面とることができた。線工費は1,000万円前後である。
世界で単価が一番安い建物といわれる前記バックミンスター フラー氏の半球形構造物は、機関車工場や或は木製でレーダーの上屋等に使用されている。
近頃新聞紙上を賑わせている屋内野球場も当然半球形となることであろう。
当所ではこの他、角形体育館も多数設計実施しており、その代表的なものは実例の項で参照されたい。前記、文部省基準案では、体育館も作製したのであるが、在来の手法を踏襲したものに偏したものの如く、構造は鉄骨のみに依存し材料選択の自由を欠いたきらいがある。
作者の案では、円形、角形を問わず体育館の如き大張間のものでも、屋根組トラスのみを軽い鉄骨とし、柱はすべて鉄筋コンクリートとし、水平トラスの代りに廂やバルコニーや見物席をとり。構造と実用とを兼ねたものを採用するよう提唱し、雨樋の如きもコンクリートの廂が兼用するという永久的なもので、而も工費は坪当り4万円以下で仕上及び設備を含み数多く完成している(実例参照)。実例の他に、学習院初等科体育館を作者の設計の如くによくいわれるので一言述べさせて戴く。これはPTAの中に設計者がおり奉仕的に設計を申出で原案を作製し、建設委員二名をPTAの中より推薦して委員会を組織して実行に移つたところ、たまたま、そのうちの一人は作者が、前記文部省の席上で一緒に体育館の基準作製に参画した人であつたので、作者を委員会に招いた。
原案の計画及び構造法は文部省の基準案よりも更に過去のものであつた。
現在建つているものは、躯体工事は鉄筋コンクリートとなつたが、肝腎な妻側の耐震壁が、鉄骨造でラスモルタル塗になつていて亀裂雨洩等の故障が多く、屋根はトタン板で廂というものが全然なく前記雨樋のとり方その他すべて作者の設計方針とは可成の違つたもの或は歪曲されたものである。
当研究所で直接設計の都立大泉学園、立正交成学園女子部(千歳烏山)、高崎市立女子高校、山崎学園富士見高校、同中学校、その他、円形校舎の最上階に数知れぬ程造つた体育館について作者の意図を見極めて頂きたい。
戦後、鉄骨コンクリートが非常に安価に出来るようになつたので、鉄骨のみで地上から造る従来の構法例えば工場、市場等も、もつと耐久力のある堅固なコンクリート構造と綜合的に組み合せて造つた方がよりよいものが安くできることを強調したい。∫-3 図書館
古来、円形書庫は角形に比し蔵書率が少ないとされているが、近来、開架式書庫の発達に伴い、却て円形の方が管理上広く使えることが判つてきた。書架を壁際に置き中央を閲覧室にする小規模のものと、反対に中央に書庫を置く大規模のものとある。書籍は非常に重量が大きいので、中央式書庫は円形の場合非常に有利であり、従つて経済にできる。一般に歩行距離が短かく、採光によく、管理も又便利である。その他、円形校舎の教室の如く、レクチュアルームをとるに便利であり、最上階には円形大講堂をとることもできる。(実例)
増築は一部半径方向に伸ばし、扇形に建増するか、全然別個に矩形又は円形を建て、渡廊下又は地下道で連絡すると、窓が塞がらずに済む。あるいは円形を中心にして放射状に足を出し、内庭を挟んで、花弁又は車輪状に外輪で包むといくらでも増築できる。∫-4 劇場および公会堂
円形ドーム及び円形ホールは音響上反響があつてよくないとされているが、実際には少しもといつてよい程影響はなく、好成績で使用中である。理由は、天井及び壁を完全に近い程吸音性とし、ステージ廻りを音響的に固くしたことであると思われる。
円形の利点は最少の表面積で最大の収容力のあること、屋根ドームが安く出来ることと外部傾斜路などがエンドレスに容易にとれること等であろう。
工期も角形に比し早く出来ると思う。これは勿論構法及び規模にもよるけれ共、あやめ池円形大劇場の場合は12月20日頃漸く基礎にかかり、3月10日に開演という超スピードであつた。(実例)
公会堂の利点としては、三角形や狭い土地にも建てられることの他、前記の利点は勿論のほか、不用となつた際、床を少しく増築すれば円形校舎の形となり、多目的に即ち学校あるいは事務所、庁舎等に転用出来ることも大きな特長ではあるまいか。∫-5 宗教建築
仏教では八蓮、八角などは円と同じく意味のあるものとされていて、聖徳太子の夢殿にも見られる。八角は円構造と殆んど同じ構造法で解くことができ、非常に経済に建てることができる。(実例)
円形も又円満、大団円などといつて宗教建築には打つてつけであり、新興宗教立正交成会の大聖堂は、ドーム直径36m、外周直径70mという大きなものである。(実例)
この他、宝物庫などにも適し、高野山に建てたいと世話する方もあつた。∫-6 病院建築
昭和28年5月8日日本経済新聞、次で同29年4月27日朝日新聞等に作者の円形建築が非常に経済的に出来るという記事が発表され次々とニュース、雑誌等に喧伝されるや、建築主の方から進んで円形建物を望む声が高くなり、円形建築に習熟しない設計者が迷惑したという実例が次々に起つた。その一つとして何でも円くさえすればよいかというので現れたのが所謂ドーナッツ型の病院で、作者の最も排撃するところであり、円形建築の発展を阻害するものとして大いに警告を発すべきものと信ずる。
その実証として、ドーナッツ型は二、三模做が続いたが、その後パッタリ途絶えてしまつた。日本全国で、作者の知る限りでは五ケ所位のものと思う。中には或設計者自ら建築主の要求を困つたものだと雑誌に公表している位で、その責任が当作者にある如く聞えるのは如何かと思われる。
現在、当研究所の作品例は、皆、病棟であつたり、臨時の外来診療棟であつたりして、綜合病院の本館のようなものは、角形が多く、作者理想の円形のものは未だ実現出来ないでいる。
伝染病棟としては一時、厚生省の推薦をうけ、全国に三ケ所実施した。当時、補助対照が坪当り9万円の時に、4万2千円位で出来たのは良かつたが、面積が非常に小さく、三階建位のもので(直径20m)、もう少し大きく、工費もあれば、今後の参考にもなり、研究にもなつたのにと惜しまれる。(実例)
その後、眼鏡型病院を本館として二ケ所設計実施し、好評にて喜ばれているが、これも又もう少し仕上げを良くすべきであつた(実例)。
中央棟に円形を建て、四方に診療棟や病棟を建てる方法は今後発展すると思う。(実例)∫-7 ホテル及び寄宿舎
日照の関係で、一日に一度は日が当るところから、独身寮やホテルには適するが、家族宿舎の如く、終日いるところには一考を要する。
スイス辺りのスキーホテルには煙突のように細長い円形ホテルが林立している写真を見る。今流行のユースホステルなどにはあつらえ向きであろう。
あまり大円形は個室には不向きで、直径20m乃至40m止りかと思う。下階のロビーのある階はどの位大きくとつてもよいだろう
箱根、熱海のような傾斜地に何故もつと建たぬのか、円形建築の知識の普及せぬのが残念である。
実例にのせた高層ホテル案は、某既成大宗教団より信者の宿泊施設として最適であるとして、模型の借用方を申込まれたことがあると聞く。もつと改良して、都心にも、レゾートにも安く良いホテルをどしどし建てたいものである。∫-8 デパート
郊外に円いデパートを建てては如何、外壁に沿つて螺旋状に自動車道をつけて屋上に登ることもできる。
都心の場合は内部の柱の配列のみ円形にして、外壁は突出し床で四角くすることもできる。内部の陳列は、角形と異なり、円周方向にエンドレスに見て廻れて工合がよく、急ぐ場合は、半径方向に最短距離で目標へ突進、ということもできて便利である。中央広間は、ショーなどにもつてこいである。
大阪某ターミナルデパートの増築の場合、構造体だけで角形ならば約5億かかるところを略計算でも約3億で充分なことが判つた。いづれ他の機会に必ず実施できると確信を持つている。(実例)∫-9 陳列場及び美術館
デパートの項に述べた如く、周囲は四角くすることもでき、特種な合理的配列ができるので、今後必ず、陳列場に使用される。自動車、機械類の大きなものにも向く。
巨匠故ライト氏のグツゲンハイム美術館は、かたつむり状に上階に登つて行くものらしい。この例のヒントを市長に告げたので、前記習志野市で作者設計の円形校舎に次で高校に螺旋床のものを二校建てられた。
このアイデアは病院にもストレッチャーが登れて面白いと思う。∫-10 自動車庫
大部古くより、中央に廻転エレベーターを設け、放射状に車庫をとつた自動車高層ガレージの案は屡々見受けられるところである。作者は円形の外周が傾斜路を螺旋形に巻きつけるのに最適であるところから、地上あるいは地下に自動車駐車場を設けることを提唱したい。
エレベーターによる上下動は古書によれば、経済的に合わぬ由であり 欧米では国庫補助を要するとされており、それでなくとも東京都庁の地下ガレージの如く、殆んど利用者 く。廃物となつたのも専らエレベーターの煩瑣によるものと思われる。斜路による場合は神戸市庁舎の一例を以てしても、非常に便利に利用されている。
円形スクリュー状の高層あるいは地下格納庫は近く多数実現すること必至である。∫-11 倉庫、冷蔵庫及び保温庫
自動車庫と同じく中央に廻転式エレベーターを設けた高層倉庫は非常に便利であると思う。
周囲の外壁の長さが如何なる形体のそれよりも最少でありながら、収容力は最大であるところから、倉庫としては最適であり、且つ放熱面積も最少であるところから冷蔵庫、逆に保温庫あるいはX線室、原子炉等に経済的に応用できる。
円形建物は密集して、互に接近して建てても、通風、採光等を妨げないので、サイロの如く林立させるとよい。而も防火、防災上も別棟とした方が利点が多い。しかし、巨大な円形倉庫も容易に出来ること勿論であるが、小規模のものでも角形より圧倒的に安く、堅固に出来るから、数多く分散するのもよい。
今後、倉庫は殆んど円形になるのではあるまいかと思う位である。∫-12 工場
円形工場は考えて見ただけでも、明るい、能率のよいものが出来そうだ。中央に向つて部分品の流れ作業を行い、中央部で組立て地下道あるいは一方向の通路で外部え運び出すもよく、又は逆に中央に材料を置き、周辺え向つて多量に同時に製品化していく方法もある。全然柱なしの大張間の建物が安くできるので、大型の組立工場などにも応用でき、又高層のものは細かい部品、薬品等に向いている。
既に、ナショナルの工場で、京都附近の国鉄沿線で円形校舎かと思うようなものが見られる。
トヨペットの名古屋の事務所も、円形校舎によく似たものが建つている。
当所設計のもので、旭電化(アデカ)の研究所は四階建の円形で完成した。∫-13 その他
以上の他 円形建物はいくらでも応用を考えられるが、それは又次の機会に譲るとして、今後は円形に限らず、大きな観点から、円形と矩形との結合とか、もつと自由な形の駆使、あるいは又別の考えから地域全体を大きな円形ドームの中に収め、原子エネルギーによつて人工気候を造る、あるいは太陽熱による大温帯地方の出現――東北地方が南九州のようになる――その地域間の交通はチューブでも、トンネルでもよい等々の考えが生れる。
あるいは逆に小さく考えて個人の家で空中に球体で、又は海中にも極地にも住むことが出来る等々。
『円形建築』日本学術出版社(1959年)



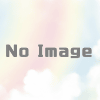
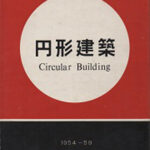
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません